完全オンラインで切り開く未来の学び――開志創造大学 情報デザイン学部を新設

日本社会は現在、急速な技術革新とIT人材不足という二重の課題に直面しています。AI、IoT、クラウド、データサイエンスといったデジタル技術が日々進化する一方で、それらを活用できる人材の育成が追いついていないのが現状です。経済産業省の試算によれば、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると見込まれており、これは日本の産業競争力や地域経済の持続可能性を大きく左右する深刻な課題です。
さらに、技術の進歩によって既存のスキルが短期間で陳腐化することも珍しくなく、社会人の「リスキリング(学び直し)」の必要性はますます高まっています。政府も「三位一体の労働市場改革」の柱の一つに「リスキリングによる能力向上支援」を掲げ、経済産業省や厚生労働省を中心に取り組みを加速させています。こうした社会の要請に応えるため、教育のあり方そのものを抜本的に見直し、変革していくことが求められています。

完全オンラインで広がる学びの可能性
こうした社会的背景を踏まえ、NSGグループの事業創造大学院大学は、2026年4月より「開志創造大学」へ名称を変更し、完全オンライン制の情報デザイン学部を新設いたします。
新設する情報デザイン学部は、「情報技術」「創造力・課題解決力」「経営管理・プロジェクト管理」の三領域を軸に、AI・データサイエンス・UXデザイン・プロジェクト管理・アントレプレナーシップなどを学びます。それらの学びを通じて、AI・データサイエンスなどの先端技術を活用し、課題解決と価値創造を実現できる人材の育成を目指します。
また、この学部は完全オンラインによる通信教育課程として開設し、学ぶロケーションや時間の制約を取り払った学習環境を実現します。学費負担を軽減しながら、地方在住でも質の高い教育を受けられるよう設計されており、社会人のリスキリングを含む多様な学習ニーズに応えることができます。
事業創造大学院大学は2006年の開学以来、「研究に基づいた実践、実践に基づいた研究」を理念に、アントレプレナーシップの形成に力を注いできました。この理念は今後も大学院の教育・研究で継承し、研究科は呼称として「事業創造大学院」を引き続き使用します。また、2026年4月には、事業創造研究科に経営科学専攻(博士後期課程)を開設し、起業・ビジネス創造の理論と実践を一層深化させてまいります。
専門学校とつながる学び――大学併修制度の可能性
開志創造大学は、全国の専門学校と提携し、大学併修制度を活用した教育体制を整えていることも大きな特徴です。NSGグループは、新潟県で「NSGカレッジリーグ」29校、福島県で「FSGカレッジリーグ」5校の専門学校を展開し、そのほぼ全てで大学併修学科を設置しています。これにより、学生の皆さんの学びはより一層充実し、専門教育と大学教育を組み合わせた幅広い学習機会を提供します。
デジタル社会の進展により、あらゆる分野で情報技術の重要性が急速に高まっています。専門学校の学びに加えて、情報技術・情報デザインを学ぶことで、将来目指す業界で、専門知識とデジタルスキルを融合させた実践力を発揮できるようになります。大学のカリキュラムも併せて学ぶことで学士号の取得も可能です。
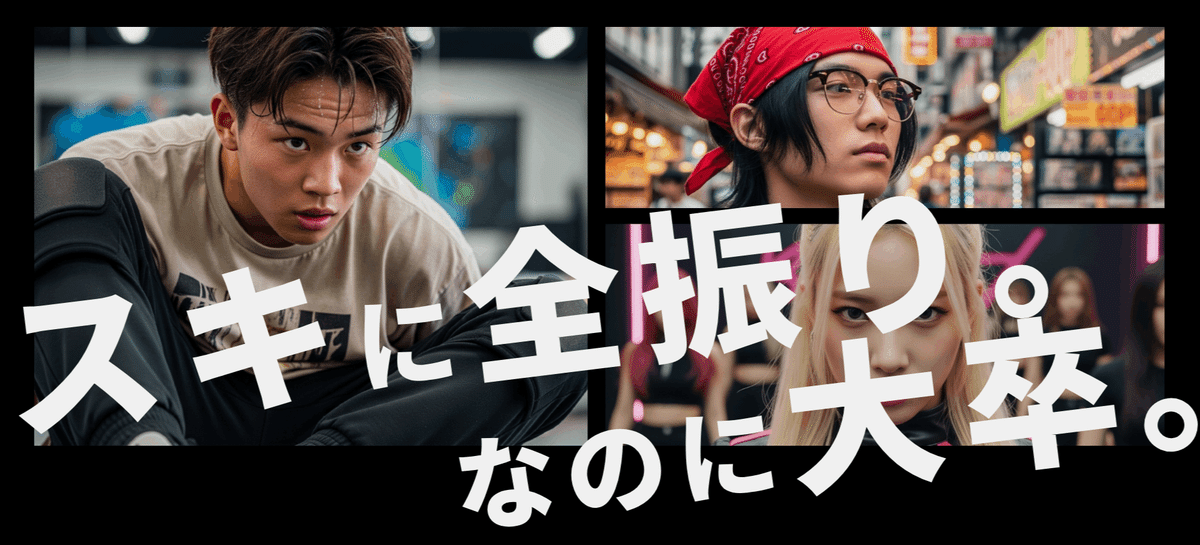
社会課題解決を担う人材を育成
開志創造大学 情報デザイン学部は、情報技術を活用して、社会における課題解決と価値創造ができる力を身につけた人材の育成を目指しています。また、「開志創造大学」という名称には、大学の将来像を見据え、学びの領域を拡張していく意志と可能性が込められています。情報デザイン学部をその第一歩として、複数の学部設置を進め、将来的には総合大学として発展することも視野に入れています。社会の変化や多様なニーズに応え、時代に求められる人材の育成に挑戦し続けるとともに、学び直しや専門性の深化を志すすべての人に対して、柔軟かつ実践的な学びの機会を提供し、各地域の持続可能な発展に貢献できるよう力を尽くしてまいります。 〆


